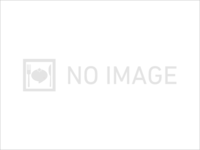万年スープ(食道楽)
万年スープ(まんねんすーぷ)は、明治36年(1903年)に出版された村井弦斎の小説『食道楽・春の巻』で赤茄子が登場する項である。
註譯
○球葱スープは球葱の大なるもの六個を細に刻みたらば深き鍋にバターを大匙三杯位溶かし葱の鳶色になるほど炒りつけ、水に漬けたるパンの割りたるものと塩と胡椒を加え水を沢山注し、十五分間余り強からぬ火にて煮たる後青味を何なりとも入れて出すべし。
○右の球葱の場合に日本葱の上等を使いてもよし。
○水を注す代りに牛かあるいは鳥のスープを注せば一層味よし。
○豌豆スープは仏蘭西豌豆の乾したるものは一夜水に漬け、生ならばそのまま洗いてザット湯煮、一度湯煮こぼして次に水とホンの少しの塩を加え二時間ほどよく煮、豌豆の柔になりたるものを掬い揚げ、摺りつぶして裏漉にし、漉したるものを前の汁に入れ、塩、胡椒、バターに味をつけ再び煮立てて用ゆ。 これも水の代りにスープを用ゆればなおよし。薄く小さく切りたるパンを五つ六つ浮かせて出すもよし。
○赤茄子スープは夏ならば生の物、冬ならば鑵詰の物を四十分間煮てバターを交ぜ、曹達を極く少し入れよく掻廻し別にスープかあるいは牛乳を沸してこの中へ注ぎ込むなり。 壜詰のトマトソースを用ゆれば便利あり。
○葱および球葱は脳を養いかつ消化液を分泌せしむるの功あり。 日本葱は蛋白質一分五厘、脂肪二厘、含水炭素四分八厘を含む。 球葱は蛋白質一分六厘、脂肪一分、含水炭素八分三厘を含む。
○葱の臭気は一種の揮発油硫化アルリールあるによる。
○豌豆は蛋白質弐割弐分、脂肪二分、含水炭素五割あり。滋養の功蚕豆に亜ぐ。
○赤茄子は蛋白質八厘八毛、脂肪一厘、含水炭素三分六厘ありて九割余は水分なり。
第三十 万年スープ
小山のかくまでに勉めし甲斐ありて中川の心も漸く大原に傾けり「なるほどそういってみると大原君も馬鹿に出来んね。
心の礼の説は僕も今に至って感心している。
しかしこういう事は僕の一量見に行かんから先ず本人の心を聞いてそれから国元の親たちへも相談しなければならん」小山「それはごもっともだが君とお登和さんとが御承知なさればお国の方はどうでもなるだろう。
モシお登和さん、コレさお逃出しなさらんでもようござる。
モシモシ」と呼べどもお登和は台所へ引込て再び出いで来らず。
程なく晩餐の用意出来たりとて下女が大おおいなる食卓を持出し来る。
小山は座を開き「これはこれはまた御馳走になっては相済まんね」中川「妹の料理を一つ味ってくれ給え。
先日君に御馳走した豚料理は原料が悪くって不出来だったがその後上出来の時は暴食先生の大原君に食べられて君に差上げないのが遺憾千万。
今日は豚料理でないよ、妙な折衷料理だが、君、このスープを一つ試み給え。
これは万年スープと僕が名を付けた新工風のスープだよ」小山「万年スープとはどういう訳だ」中川「これは朝鮮にある牛頭スープから思い付いたので、朝鮮人は何処の家でも台処に大きな鉄釜があってその中へ牛の頭を一つ入れて外の野菜でも鳥の骨でも何でも打込んで一年中下へ火を焚いている。
そうして毎日そのスープを飲むが牛の頭は一年に二、三度より取かえない。
しかし毎日煮ているからスープの味は非常に佳くって滋養分も多い。
僕のはそれを折衷して牛肉の骨付という一番廉い処を買って大きな鍋へ入れて火鉢の上へかけておく。
その中へ鳥の骨も入れれば野菜は何でも入れる。
スープを煮出すのだから上等の処は要らん。
葱を切ても人参や大根を切ても頭と尾の捨てるような部分を掃溜へ捨てないでスープの中へ入れる。
そうして火鉢の火の明いている時は夜でも昼でも掛け通しておく。
全体日本人の家では何時でも火鉢に火が起っていて鉄瓶がチンチン沸騰っている。
あれは不経済の極点で、西洋人の家では三食の外にストーブを焚く事がない。
といって日本風の家では客が来ると火を出し茶を出すから火を絶す事も出来ん。
そこで無用な火気を利用するためにこの万年スープをかけておく。
客が来て茶を出す時には湯沸しで直ぐ沸くから少しも困らん。
それに大根や人参の頭と尾を掃溜に捨てるのも惜しい事だ。
スープにすれば味も出るし滋養分も出るから即ち廃物利用主義でこの万年スープを案出したのだ。
最初原料を入れてから毎日火へかけて四、五日目位からスープが非常に美味うまくなって、これを食べると普通の牛肉スープや鳥スープはモー食べられんね、その代り野菜の分量が骨や肉の分量より多くなり過ぎると味が悪い。
僕は十日目に一度原料を取かえる事にした。
夏になると牛肉や鳥肉を廃して魚の骨を捨てずに万年スープを作るが魚のスープには魚肉を少しでも入れてはいかん。骨ばかりに限る」と一々講釈付きの御馳走。
客はスープを喫しながら「なるほど妙な味だ。僕は牛肉や鳥肉でばかりスープを作らせるが高いものに付くよ」中川「それでは贅沢過ぎて味も悪い。
僕の家では球葱スープだの豌豆スープだのと野菜ばかりのスープも出来るよ」と相変らずの料理自慢。
良ありてお登和が西洋皿へ御馳走を盛りて出で来る。
小山急に振返り「モシお登和さん、今のお話しはね」と語り出さんとするにお登和嬢皿を食卓の上に置きて再び台所へ逃げて行く。
参考文献
- 『食道楽・春の巻』:明治三十六年(第三十・万年スープ)